月額5000円以下で使える通信教育サービス比較
「塾に通わせたいけれど費用が重い」「家庭学習だけだと続かない」――そんな悩みに、月額5000円以下の通信教育は現実的な選択肢です。
ただし、安さだけで選ぶと失敗します。鍵は、子どもの性格・家庭の生活動線・親の関与スタイルに合うかどうか。
同じ教材でも“化ける家庭”と“続かない家庭”に分かれるのは、ここが合っているかで決まります。
本記事では、代表的なサービスを比較しながら、やり切る仕組み・ありがちな落とし穴・導入の初動プランまで具体的に整理します。

料金と仕様は変動します。
本記事は「5000円以下で利用できる(または近い価格帯の)代表プランがある」サービスを中心に解説しています。最新の料金・対応学年・端末条件は必ず公式サイトをご確認ください。
第1章:選ぶ前に“土台”を決める(ここが9割)
最初に決めるのは教材名ではありません。どうやって毎日回すかです。
- 学習時間の固定: 平日は15分、休日は30分など時間枠を先に決める
- 媒体の役割分担: 平日はタブレット、休日は紙ノートに書く――のように使い分ける
- 親の関与レベル: 丸つけをする/見守る/任せる――どこまで関わるか先に合意
- 90日ルール: 一度選んだら3か月やり切ってから乗り換え判断
ありがち失敗: 体験版を渡り歩いて、全部“ちょっとずつ”。結果、どれも定着しない。
対策は単純で、同時に触るサービスは必ず1つに絞ることです。
第2章:代表的な通信教育サービス比較(5000円以下帯)
| サービス | 媒体 | 対象タイプ | 親の関与度 |
|---|---|---|---|
| 進研ゼミ 小学講座 | 紙/タブレット | 学校授業を着実に定着 | 中 |
| スマイルゼミ | 専用タブレット | 自動丸つけで自走 | 低 |
| Z会 小学生コース | 紙/タブレット/添削 | 思考力・記述を強化 | 中〜高 |
| スタディサプリ(小学) | 動画+演習 | 苦手単元を集中補強 | 低〜中 |
| すらら | アダプティブ学習 | つまずきの学び直し | 中 |
進研ゼミ 小学講座(チャレンジ/チャレンジタッチ)
学校の授業と同じ流れで復習・定着が進むため、テストの取りこぼしを減らしやすいのが強み。
紙とタブレットを切り替えられるので、家庭のスタイルに合わせやすい設計です。
活用の勘所: 平日はチャレンジタッチで15分、休日は紙ワーク+親の短いコメント。
「見てもらえている」が続ける燃料になります。
体験談:
赤ペンで一言コメントを添えるだけで、提出のリズムが安定。
「丸つけしてもらうのが嬉しい」と子どもからプリントを持ってくる回数が増えました。
スマイルゼミ
専用タブレット1台で完結。自動丸つけとアニメ解説で「できた!」を小刻みに積み上げられます。
机に向かうのが苦手な子の“入口”づくりにも有効です。
活用の勘所: ごほうび条件を“時間”から“ユニット数”に変更。
「1ユニット終わったら外遊びOK」にすると、取り組み開始までのグズグズが消えます。
体験談:
夕方の声かけを「今日の分やった?」の一言に固定。
親の関与を最小化しても習慣化でき、ノーストレスで回るようになりました。

Z会 小学生コース
「良問・添削・言語化」で、“わかった気”から“説明できる”へ引き上げる教材。
短時間でサクサクより、じっくり考える時間に価値を置く家庭と相性が良いです。
活用の勘所: 解答解説を“音読→要約→自分の言葉で説明”までやる。
添削の赤コメントを次の学習で意識すると、記述が目に見えて洗練されます。
体験談:
最初は「難しい」と感じたが、親子で“なぜそう考えたか”を語る時間が増えた。
評価軸を点数から「説明できるか」に変えたら、表情が変わりました。
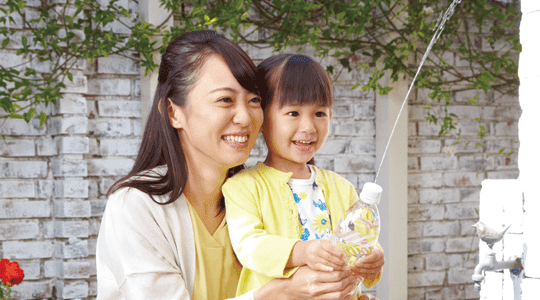
スタディサプリ(小学)
有名講師の授業を単元ごとに視聴できる“学びの救急箱”。
苦手単元の“ピンポイント復活”に強く、兄弟での共用もしやすいのが魅力です。
活用の勘所: インプット(授業視聴)→ アウトプット(演習)→ 仕上げ(その日のうちに)を1セットに。
「見ただけ」で終わらせない設計が命です。
体験談:
算数の分数文章題を繰り返し視聴。
その日のうちにノートで解き直す習慣にしたら、苦手が短期間で解消しました。

すらら
AIが理解度を判定し、必要に応じて自動で“戻り学習”を提示。
学年をまたいだ穴を埋めやすく、基礎の学び直しに強い教材です。
活用の勘所: 思い切って1〜2学年戻る勇気。
“到達度ベース”でカリキュラムを組むと、焦りが消えます。
体験談:
文章題の土台を1年分戻って再学習。
可視化された進捗で「ここまで追いついた!」が実感でき、自己効力感が上がりました。

第3章:メリット・デメリットを“親の負担”で見直す
- 紙中心: 書く力・図形に強い。丸つけの手間は発生。
- タブレット中心: 自動丸つけで楽。ノートが白紙になりやすいので週末に紙を別枠で。
- 動画中心: 理解は速い。演習設計を親が握らないと“見ただけ”で終了。
よくある失敗: タブレット一本で回し、6年直前に記述力不足が発覚。
早期から「書く日」をカレンダーに固定しておくと、偏りを回避できます。
第4章:家庭別・選び方フレーム(性格 × 生活動線 × 伴走)
- 性格: コツコツ型→紙も相性良し/飽きやすい→タブレットで小刻み達成/考え抜くのが好き→Z会
- 生活動線: 端末を共有→紙中心で安定/移動学習したい→タブレットや動画
- 伴走: 丸つけできる→紙もOK/忙しい→自動丸つけや進捗可視化を優先
迷ったら、当てはめて最も“負担が軽く回る形”を選ぶのが正解です。
第5章:導入から14日の初動プラン(テンプレ)
- Day1–2: 学習時間帯を固定。机の上は教材とタイマーのみ。
- Day3–7: 毎日15分を死守。週末は紙ノートで“書く”時間を30分。
- Day8–10: つまずき単元をリスト化。スタディサプリ等でピンポイント補強。
- Day11–14: 親はコメントを短く。達成の可視化(カレンダーに○)で手応えを残す。
この2週間で“やる時間”と“回し方”が固まれば、その後は惰性で回ります。
第6章:Q&A(本音で回答)
Q. 月5000円以下で受験までいける?
基礎固めは十分可能。過去問・記述・学校別情報は模試・添削・短期講座で補うのが現実解。

Q. 親が教えれば節約できる?
短期的には節約可。ただし、親子関係の摩耗リスクが高い。親は“先生”ではなく、計画と習慣の伴走者に徹するのがおすすめ。

まとめ:5000円の価値を最大化するコツ
- 選ぶ前に“回し方”を決める(時間・媒体・伴走)
- 同時並行はしない。1つを90日やり切る
- タブレット派も週末は必ず紙に書く日を入れる
- つまずきは動画やアダプティブでピンポイント復活
- 必要に応じて模試・添削を短期投入して仕上げる
教材そのものよりも、“どう使い倒すか”で伸び方は変わります。
家庭の現実に合う形で仕組み化し、淡々と回していきましょう。
関連記事





