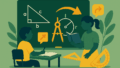中学受験で親が家庭教師役は危険?
中学受験を考えるとき、「塾に通わせる」「家庭教師をつける」などいくつもの選択肢があります。
その中で「親が家庭教師のように教えれば節約にもなるし、子どもに合った指導ができるのでは?」と考える家庭も少なくありません。
一方で、親が勉強を直接教えることには大きなリスクも伴います。
この記事では親が家庭教師役を担うメリットと危険性を整理し、無理のない家庭学習の形を探ります。さらに、実際の家庭が経験した「失敗と切り替え」の体験談も紹介します。
この記事でわかること
- 親が家庭教師役を担うメリットとデメリット
- よくある失敗例と成功例
- 家庭学習で親ができるサポートの範囲
- 塾なし受験や他の学習手段との比較
- 親が失敗して塾に切り替えた体験談
親が家庭教師役を担うメリット
まずは親が直接子どもに教えることで得られる利点です。
- 費用を抑えられる:家庭教師や塾の費用は年間で数十万円規模。親が教えることで大幅な節約が可能。
- 子どもの性格を理解している:わが子の苦手や癖を知っているため、個別最適な声かけができる。
- すぐに対応できる:宿題でつまずいたとき、その場で解説できるスピード感。
特に小学低学年のうちは「親が横で見てサポート」する形で成果を上げている家庭もあります。

親が家庭教師役を担う危険性
一方で、親が「先生」になることで生じるリスクも大きいです。
- 親子関係の悪化:「なんでできないの?」「前も言ったでしょ!」と感情的になり、口論に発展するケースは非常に多い。
- 教え方の難しさ:専門の講師ではないため、解説が長くなり逆に子どもを混乱させることも。
- 子どもの依存:常に親に頼る学習姿勢が身についてしまい、自分で考える習慣が育ちにくい。
ある母親は「最初は節約のために自分が教えていたが、毎日のように口論になり、子どもが勉強を嫌いになってしまった」と振り返っていました。
親子関係を壊さないために、あえて塾に任せる選択をしたといいます。
よくある失敗例と成功例
失敗例
「理科の解説で専門用語を使いすぎてしまい、かえって子どもが理解できなくなった。プロが子どもの言葉で説明する大切さを痛感した。」
「つい比較して“〇〇ちゃんはできてるのに”と言ってしまい、子どもが自信をなくした。」
成功例
「算数の計算問題だけは毎朝一緒にやると決めた。短時間で済む分、口論にならず基礎力だけは定着した。」
「子どもが説明を親に“教え返す”形式にしたら、理解度チェックにもなり、親子関係も良好に保てた。」
体験談:親が失敗して塾に切り替えたケース
ここで、第三者として耳にした「実際の家庭の声」を紹介します。
「最初は“塾代を節約しよう”と考えて、母親が国語と算数を教えていた。最初のうちは上手くいっていたが、次第に教え方をめぐって衝突が増え、子どもが机に向かうのを嫌がるようになった。
結局、小4の途中で塾に切り替えたところ、授業をプロに任せることで家庭の雰囲気も落ち着き、親はサポート役に回れるようになった。」
この家庭は「もっと早く塾に任せていれば親子関係を壊さずに済んだかもしれない」と振り返っています。
親が「先生役」から「応援者」に回るだけで、子どもの態度や学習への意欲がガラッと変わることもあるのです。
親ができるのは「伴走者」役まで
結論として、親が完全に家庭教師になるのはリスクが大きいといえます。
しかし、伴走者としての役割であれば非常に効果的です。
- スケジュール管理(計画を立てる・見直す)
- 学習環境の整備(静かな場所・デジタル教材の導入)
- モチベーションのサポート(声かけ・小さなご褒美)
- 解けなかった問題を一緒に調べる姿勢を見せる
つまり「教える」よりも「支える」方に回った方が、結果的に子どもの自主性を育てられるのです。

まとめ:親は「先生」ではなく「応援者」に
中学受験で親が家庭教師役を担うことは、短期的には効果があるかもしれません。
しかし、長期的には親子関係の悪化や子どもの自主性低下などのリスクを伴います。
親の役割は「教える人」ではなく「環境を整え、支える人」。
塾や教材に任せつつ、親は伴走者として寄り添う姿勢が、子どもの力を伸ばす近道です。