中学受験 算数 図形問題を得意にする練習法
中学受験において「算数の図形問題」は、多くの子どもがつまずく分野のひとつです。
立体の展開図、角度の計算、相似や面積比など、学校の授業では十分に扱わない単元も多く、塾の授業で初めて触れて苦手意識を持ってしまう子も少なくありません。
一方で、図形問題を得意にすると算数全体の得点力が一気に上がります。
なぜなら、図形は「一度コツを掴むと応用範囲が広い」からです。
この記事では、算数の図形問題を得意にするための練習法を具体的に紹介しながら、親が家庭でできる工夫やサポートの実例も交えて解説します。
この記事でわかること
- 図形問題が苦手になる典型的な理由
- 図形を得意にするための練習法
- 家庭でできる親のサポート
- 体験談:成功例と失敗例
- 受験準備にかかる費用との関係
なぜ図形問題は苦手になりやすいのか?
多くの子どもが図形を苦手とする理由は、以下のように整理できます。
- イメージ力が追いつかない:立体や展開図を頭の中で回転させる力がまだ弱い。
- 公式暗記に頼りがち:相似比や面積比などを丸暗記してしまい、応用が利かない。
- 問題演習の量が不足:図形問題は「慣れ」が必要だが、他単元に比べ演習量が少ない。
つまり「感覚的にわかる」段階に到達する前に嫌いになってしまうのです。

図形を得意にする練習法
①紙と鉛筆だけでなく「作って動かす」
展開図や立体は、実際に紙を切って折る・展開するなど「手を動かす体験」が効果的です。
頭の中だけで処理するのではなく、物理的に形を扱うことでイメージ力がぐんと上がります。
②典型パターンを繰り返す
算数の図形問題はパターン化されやすい分野でもあります。
「角度の追い方」「補助線の入れ方」などを繰り返すことで、“図形センス”を積み上げられます。
③図や補助線を自分で書く習慣をつける
解答を読むだけでは身につきません。
自分で図を描き、補助線を試行錯誤するプロセスこそが本当の練習になります。
④スモールステップで積み上げる
いきなり過去問に挑むのではなく、基礎レベルから徐々にレベルアップ。
「基本問題→応用問題→発展問題」と進めることで、自信を積み重ねやすくなります。
家庭でできる親のサポート
図形問題に強くなるには「継続した練習」が必要ですが、親ができるサポートには限界もあります。
それでも、家庭でできることは次のようなものです。
- 一緒に紙で立体を作ってみる
- 補助線を引く過程を「声に出して説明させる」
- タイマーを使い、短い集中時間で演習させる
- 「今日できたこと」を小さく褒める
親が“先生”になる必要はありません。
「伴走者」として一緒に試してみる雰囲気をつくることが、子どもの安心感につながります。
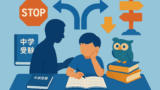
体験談:成功例と失敗例
成功例
「立体を折り紙で作る遊びを取り入れたら、展開図の問題を怖がらなくなった。遊び感覚が学びにつながった瞬間だった。」
「子ども自身が補助線を引くルールにしたら、最初はごちゃごちゃだったけど、半年後には自分で図形を整理できるようになっていた。」
失敗例
「難問ばかり与えてしまい、子どもが完全に図形嫌いに。結局、基礎に戻すのに時間がかかった。」
「親が横で口を出しすぎて、子どもが“もう図形は嫌だ”と拒絶するようになってしまった。」
図形問題対策と費用の現実
図形問題を克服するには、教材や講座を組み合わせる家庭も多いです。
市販教材・ドリル・オンライン講座を使えば低コストですが、個別指導や図形特化の講座は年間数十万円規模になることも。
「図形問題のためにそこまで費用をかけるべきか?」と迷う親も多く、塾や家庭教師に任せるか、家庭学習で工夫するかは家庭ごとの判断です。

まとめ:図形を「怖い」から「楽しい」に変える
算数の図形問題は、多くの子どもにとって壁になります。
しかし、手を動かす体験・典型パターンの反復・自分で図を描く習慣を積み重ねれば、必ず得意分野に変えることができます。
親ができるのは「無理に教える」のではなく、工夫を一緒に楽しむこと。
図形を“怖い”から“楽しい”に変えられたとき、中学受験の算数全体に大きな自信が生まれます。


